お墓を建てることを「建墓」と言います。墓地・霊園が決まったら(抽選が必要な公営墓地の場合は当選してから)、建墓の計画を建てましょう。
寺院墓地ではまず寺院にご報告と相談を
寺院墓地の場合は、お墓の開眼法要や納骨法要などをその寺院に依頼することになります。そのため、時期やお墓の形態などについて、事前に相談する必要があります。建墓への宗教的なアドバイスも、有効に活用したいものです。
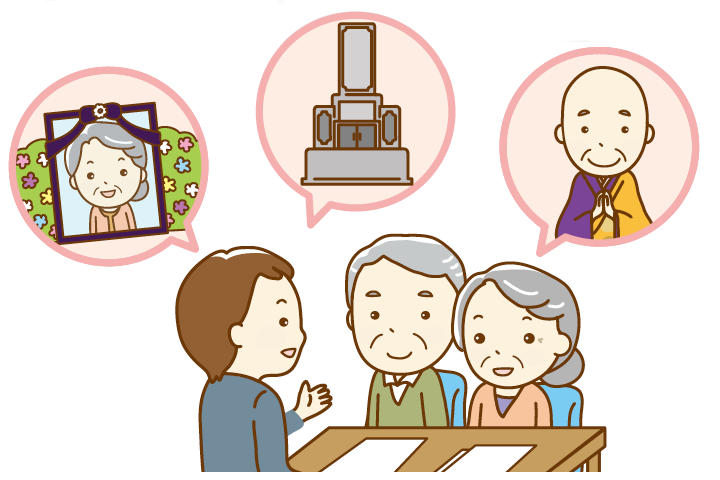
お墓を建てることを「建墓」と言います。墓地・霊園が決まったら(抽選が必要な公営墓地の場合は当選してから)、建墓の計画を建てましょう。
寺院墓地の場合は、お墓の開眼法要や納骨法要などをその寺院に依頼することになります。そのため、時期やお墓の形態などについて、事前に相談する必要があります。建墓への宗教的なアドバイスも、有効に活用したいものです。
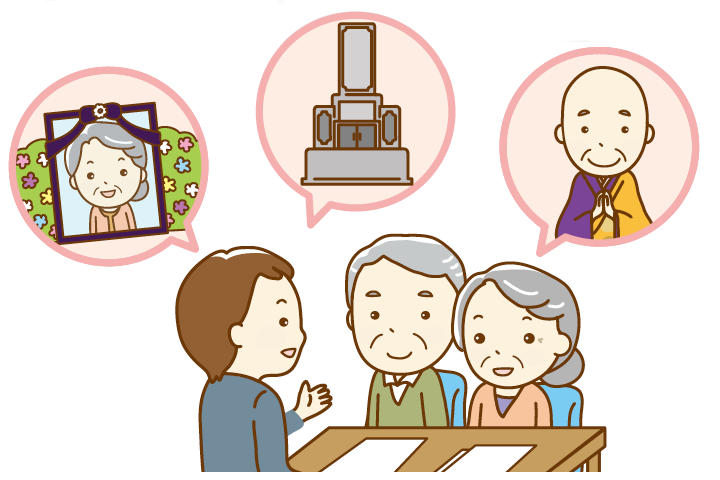
墓地にどれだけの費用をかけられるか、予算を考えておきましょう。
永代使用料・墓石・工事費・管理料・付属品などの他、開眼法要や納骨のための費用が別途必要となります。お墓自体の値段は墓石の大きさや施工内容、石の種類などで決まります。お墓の敷地が広い場合には、墓誌や燈籠などの付属品を設置することもできます。

石材はぜひ見学に行きましょう。実際の石は、写真や見本とはまた違った印象を受けると思います。石材店が決まっているのなら、過去に施工したお墓を見せてもらうのも良いでしょう。
最近では墓石の輸入も盛んになり選べる石材も増えました。和風墓(和墓)では落ち着いた色合いの石が多いですが、洋風墓(洋墓)ではさまざまな色合いの石が利用されています。また、加工によっても見え方が大きく変わったりもします。最近では自然石風のお墓も人気です。ただし、石材店によっては取り扱っていない石・加工もあるので、石材にこだわるのであれば業者選びの段階から注意する必要があります。
お墓を建てる墓地・霊園の環境をよく理解している石材店を選ぶのがおすすめです。石材店とは建墓だけでなく、何かあったときの相談や修理もお願いすることになります。気軽に相談できるところ、しっかりと説明をしてくれるところを選ぶことが大切です。

予算やお墓のイメージが固まったら、石材店と具体的な打ち合わせに入ります。
選んだ墓地・霊園に予算を当てはめれば、区画の大きさや石材などの検討がつきます。区画を優先するか、気に入った石材を使うことを優先するか、それとも彫刻や付属品を優先するか、実際の予算の割り振りを石材店と一緒に詰めていきましょう。
納骨の日が決まっていれば、そこから逆算して発注しましょう。注文から建墓までに最低でも1か月半~2か月は見ておく必要があります。できれば2~3ケ月の余裕が欲しいものです。
墓石に刻む文字は、宗派によって違います。戒名や宗派の名号・題目・家名・家紋などさまざまです。洋風墓(洋墓)の場合、従来の題目にこだわらない傾向があります。故人の座右の名であったり、遺族からのメッセ-ジであったりと自由に作ることができます。

お墓の石材やデザインが決まったら、外柵の有無やどのような基礎工事を行うかなど、細部の打ち合わせに進みます。「思ったより費用が増えてしまい、予算オーバー」ということにならないように、内容や金額はしっかり確認しておきましょう。

遺骨を納骨する際には、埋蔵許可証が必要になります。死亡届を出すときに、「死体火(埋)葬許可証」の交付申請書を役所に一緒に提出し、「死体火(埋)葬許可証」の交付を受けます。交付された許可証は火葬場に提出すると、火葬済みの証印が押され、埋葬許可証となります。納骨は後になることが多いので「死体火(埋)葬許可証」を紛失しないよう、遺骨と一緒にしておくと安心です。納骨をする際には、墓地の管理者に埋葬許可証と墓地の使用権利書を提出します。